日本の人口は減り続けている。
労働者を求めている「行政」は国外街から「労働者」を呼び、また都市部ではAIによって多くの仕事がなくなるだろう。
機械化を推し進めた、工場式学校教育を推し進めた結果、日本に生まれることを望んでくる子どもが減った。
少子化が悪い訳ではない。
人口減少は悪いことではない。
行政は、お金の使い方「しあわせ」のやりくりをしなおしたらいい。
「土木」にお金をかけて、経済活動、消費活動を活性化させて、「お金」のために。。。。
それが「しあわせ」になっているだろうか。
僕が自分自身に問いかけないといけないことだが。
放課後児童クラブの研修に行った。
そこで役所の人が話しているのも同じことだった。
「少子化は、よくない。」
安心して子どもを育てられる環境を作ろうとしてる、それが「定期テスト対策」的に。
少子化という現象に、バイアスがかかっている。
「子育てがしやすいように」はいいけど、「たくさん産んでくれるように。たくさん仕事をしてくれるように」という価値観にどう向き合うか。行政は、税金を増やしたいのだ。なぜ税金が一定量必要になるか。それは「経済のインフラ」には大量の資本が必要だから?
富山県のデータ
2020年には65歳以上が30万人
2060年には15〜65歳未満が30万人
2060年には子ども(15歳未満)ひとりにたいして大人5人、65歳以上6人。
ということは、15〜65歳未満の人数と65歳以上の人数があまり変わらない。。。
放課後児童クラブ、子育て支援、婚活支援をしても、間に合わない。
「定期テスト対策」的な政策、しかたないね。日本だもの。
ーーーーー
だかがオトノネをつくりました。
僕が、僕らしくいられる場所。
僕が僕らしくいられる場所に共感してくれる人が、これる場所。
ーーーーーー
「定期テスト対策」的な政策、しかたないね。僕はあきらめています。呆れた顔をして。
簡単なことなのに、それをしない。
学校を変えればいいだけなのに、それをしない。
できない。しかたがないね。
最初に入れるメスが、「土木」「機械」であって、「人間」ではない。
これが致命的に、オトノネとは違う。
放課後児童クラブは世の中の役にたっているよ!がんばれ!というメッセージを送っても、放課後児童クラブのスタッフが安い給料で働いている現状には触れない。福祉の世界がブラックに染まっているのが、日本だ。福祉の世界は、ブラックだ。政策として、ブラックだ(もうアメリカでは破綻した制度を、誰かが、既得権利を維持するために続けている)。だから事業所は「しくみ」をよく考えないといけない。無理に利用者を増やして、利益をあげようとしているハードワークな職場で働いている心あるお母さん、ハートワークをしたいお母さんに、オトノネにきてほしい。「第一選択肢」になるようなオトノネになりたいとおもっています。
利益を得るために、定員を増やす。
労働者を酷使する。
これが、一般的な福祉の現場です。
(そうじゃない事業所もありますよ、もちろん)
ーーーーーーーー
オトノネは「放課後児童クラブ」を元にして《放課後の学校》を作ろうとおもいたった。
お金がなくて働いている人のための場所ではない。
働きすぎて長時間労働している人に「頑張って働いてね!その間、子どもを預かるよ!」と言う場所でもない。
経済成長を夢見させる人たちに加担をしたくはない。だってもう終わっているもの。
経済成長のために、「土木」や「機械」のために税金を流すためにおとのねをするのではない。
(けどそんな規定はないから、おとのねが放課後児童クラブの補助金をもらっても、いいわけです)
っていうか、法律を見直して、「本音」に気がついた。
放課後児童クラブは「厚生労働省」の管轄である。
(認定こども園は、内閣府を筆頭にした文部科学省と厚生労働省の連名であったようにおもう)
厚生労働省は、「第二の学校」として、放課後児童クラブを作っている。
あるいみ、おとのね の友達になれる。
放課後児童クラブの設備運営基準
第五条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。
放課後児童クラブ運営指針
3.放課後児童クラブにおける育成支援の基本
(1)放課後児童クラブにおける育成支援
放課後児童クラブにおける育成支援は、子どもが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、安全面に配慮しながら子どもが自ら危険を回避できるようにしていくとともに、子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な育成を図ることを目的とする。
これを、実際に、やろうとしているのが、厚生労働省。
ともだちになってもいいけど、補助金増やしてほしい。
(これにも歴史がある。補助金狙いで悪い人たちが、たくさん、放課後児童クラブに手を出したことがあるのだ)
小学生、中学生、高校生が文部科学省の管轄だけだったのが、時代の流れに乗じて、厚生労働省が小学生にも「政策」の手を伸ばせるようになったということ。学校の外で子どもと関わる場所をつくろうとする意図を感じる。
ーーーーーー
おとのねの「放課後の学校」は
宿題をする場所ではない。
時が来るのを、待つ場所でもない。
子どもの叫び声が耳をつんざく場所ではない。
大人の叫び声が耳をつんざく場所ではない。
創造的になれる場所とはどんな場所か、おとのねさんが見つけていく場所、といえば、より正確だろうか。
ーーーーーーーーーー
放課後児童クラブでは「40人」の時、補助金が一番多く出るようになっている。
この規模の子どもたちが学べる場所をつくる資本(人とお金)はおとのね には、現段階で、ない。
40人は、学校のひとクラスの規模。
この人数を確保する場所を、民間が用意することが、現実的なのだろうか。。。。
けど将来的に、おとのねが「40人」を目指すこともできるだろう。
その「しくみ」をつくれれば。
ーーーーーー
場所がいる(お金が必要)。
人がいる(大人、そして、おとのねの文化を伝えてくれる子ども)。
おとのね のシステムとして、所属一年後からは、料金が減るしくみをいつも考えている。
子どもが先生になる分、大人の先生が助かる。
という仕組みだ。
(といっても、インドネシアの孤児院は、本当に、子どもが足の踏み場もない場所で、身を寄せ合って眠っている。みんな笑顔だ。学校、地域でストレスをうけず、気楽にやっているから。日本とは現状が違う。)
ーーーーーーー
全国的に、人口は減っているのに、世帯数が増えているという統計データがあるらしい。
富山県で家が建ちまくっている現象をよく説明しているとおもう。
富山県の場合、
「共働き」が多い理由も、ここにあるかもしれない。
「ご近所づきあい」をしなくてはいけない古い地域は、めんどくさい!とおもう人が増えてきているのかもしれない。
新しい時代は来ている。
ーーーーーー
経営の段階として、今は、身を削って「20人」にして資本として「人」と出会う時期かもしれない。
おとのねさんが「まいった!やっぱ無理!」と思ったら、、、、みんなに相談します。
計算し直しましょう。
半額です!
月額3万円。
英語の値段が「込み」だったのを、別料金にします。
月額1万円を足してください。(週一回、1時間で8000円が相場です)
やっぱり20人は多すぎます。
それが「ふつう」になっているので、お母さんにはわからないかもしれませんが。。。
やっぱり10人にします。
けど月額4万円でやります。
人が雇える値段ではありません。
福祉の現場は、低賃金労働者を作り出しています。(福祉の現場で働いたことのあるお母さんなら、ご存知でしょう)
福祉が、貧困を作り出しています。
オトノネはそれをしたくありません。
安い賃金で人を雇おうとはおもっていません。
貧困の連鎖をオトノネがつくることはしたくありません。
だめですか?
安くしないといけないなら、誰かを安く雇うことになります。
安くしようとして人数を増やしたら、保育園状態になります(空間が保証できません)。
オトノネの特色を出しましょう。
学校では教わらない、自主性・創造性・社会性を《放課後の学校》で育てましょう。
学校で教わるのは、従順性・忍耐性・集団性です。
とはいいながら、子どもは勝手に育っていきますが。。。。
どうしたらいいのでしょうか。
オトノネは「お父さんお母さん」と一緒に学びの場所をつくりたいとおもっています。
子どもを「まかせる」のではなく、「一緒に」です。
保育士、学童、福祉の現場、学校どれも違うかもしれない。。。
もしかしたら、オトノネかもしれません。
多様な選択肢の中のひとつに、オトノネを入れてほしいとおもいます。
大人を犠牲にするか。
子どもを犠牲にするか。
どちらでもない、心ある道はないだろうか。
おとのねさんは、今日も悩んでいます。
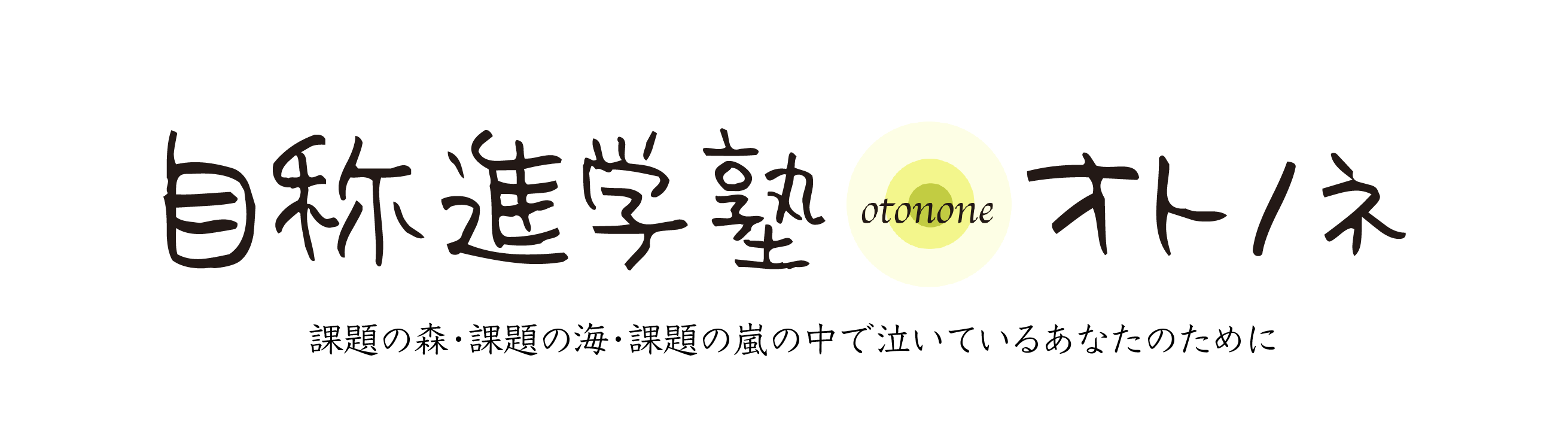
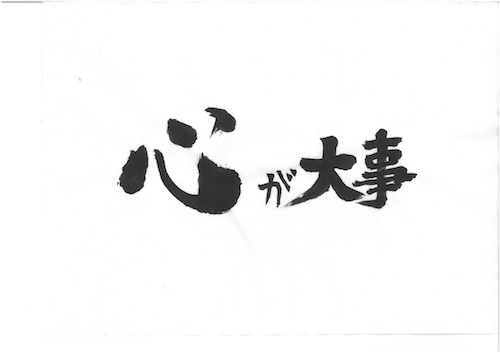
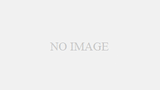
コメント