若者による暴力はいじめだけではない。
家庭内で、ワガママを貫き通すことも、暴力になる。
とあるケースでは、若者が年寄りのお金を盗んだり、お金を要求して、お金を渡さなければ暴れる、殴る、罵る、という。
泣く、暴れる、脅す。
暴力は習慣化する。暴力を認めることによって。
気質的に暴力に向かわずに引きこもるケースもある。
暴力は、習慣が生み出す。
それは学校の中であっても、家の中であっても。
暴力に対して、どのように振る舞えばいいのか?
暴力、という言葉を使っても伝わるはずがない。
暴力を使って他人の行動を変えることが有効でなくなればいい。
他人は、環境の一部。
見慣れない人、暴力が習慣化していない人との関わりが増えてもいい。
暴力が習慣化した場合、どうするのか。
民法上、親権は義務として働く。
(親権者)
第818条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。
(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。
だがこの習慣化した暴力を、親権者だけでどうにかできるものでもなさそうだ。
子育てが暗いイメージ、辛いイメージを持っているのは、年寄りの孤独感にあるような気もする。
専門機関に相談?手探りするしかないのかもしれない。
もし本人が「自分は暴力をすることが嫌なのだけれど、ついついやってしまう」のであれば、認知行動療法を試すのもいい。まずは本人に聞いてみるといい。「あなたがしていることは暴力だ、ということは、わかってる?」
わからない、と答えたなら。
聞いてみてもいい。
どうして暴力を振るうの?
暴力を受ける人は何を思っていると思う?
暴力は、その人にとって、悪いことなのだろうか。
暴力をしていることを、その人はどう思っているのだろう。
多分、恐らく、察するに、わがままを聞いてくれないこと、わがままを叶えてくれないことは暴力であるから、こちらが暴力で抗議をしてもそれは悪いことではない、と考えているのかもしれない。学校などでは、多くの場合、デフォルトで、生徒は暴力を受けている。violateされている。だからいじめも、学級崩壊も、あらゆる暴力行為も、彼らにとっては「目には目を」の返報性の原理に基づいた一貫性のある行動に過ぎない。
わからないけれど。
そうしたら、筋が通る。
学校は自分の暴力性を無力化するために、学校が生徒に対して行っている暴力は顧みることがあるだろうか。学校の暴力は暴力として認定されていないのだろうか。これは責務の問題にもつながっているように思う。暴力、という言葉は、表層的にしか理解されていないのが事実ではないか。
お金を持っている、決定権がある、力を持っていることが、暴力と結びつく。
そうして暴力が連鎖したり、習慣化するのだろうか。
実際は、どうなのだろう。
気になる。
どうなのだろう。
暴力はどこから生まれてくるのだおる。
怒りの表現である。
と言えるかもしれない。
だとしたら、暴力という表現以外の「選択肢」がないことが、若者にとっては困りごとになっているのかしらん。だとしたら、本人は暴力によって怒りを表現するしかない。けれども、それ以外にも怒りという感情を世話する方法がある。選択肢を、若者は知らないだけかもしれない。
こうした感情の技術を、若者は求めているのだろうか。
怒りという感情を取り扱う心の技術を、若者は求めているだろうか。
もし逆にその怒りを暴力によって押さえ込んだら?
その怒りの感情は、どうなるのだろう。
年寄りも、怒りに対して、怒りで応えていないか。
怒りをお世話することを、年寄り自身がデモンストレーションできないのか。
誰もが感情のマネジメントをうまくできるわけでもない。
ーーー
価値判断、判断基準のない若者がいる。
誰かに決めてもらうことを習慣化する若者がいる。
年寄りは、判断したことへの結果に対して手助けをしているだろうか。
さまざまな判断基準があることを伝えているだろうか。
判断を恐れる心がある。
判断するにも基準がない心がある。
良い悪いの判断は、誰かの反応によって変わる。
だから、暴力を受け入れてくれるなら、自分の利益のために、暴力することは悪いことではない。
と、判断しているのかもしれない。
心の仕組みというのは、不思議なものだ。
ーーー
自立した人間というのは、他人に礼儀正しく依存する人間だ。
礼儀正しい依存というものは、かくも、困難なことなのだろうかと、年寄りは、そう思った。
学校でそんなことこれっぽっちも教わらないなぁと、年寄りは思った。
ーーー
年寄りは若者の将来を憂う。
お母さんと呼ばれる人は、特に憂う。
大丈夫なのだろうか。
不安を世話する方法はいくつかあるが、一つには、行動すること、がある。
その行動の先が子どもなのか、お母さん自身なのかが、問題だ。
「子どもに伝わらない。どうしたら?」
他人は変えられない。
変えられるのは自分だけ。
自分が変わったら他人も変わる。
変わらないものは変わらない。
何が変わるかは、自分が変わってからのお楽しみ。
自分のために、一人の人間として、自分のために喜んでできることを一つでも増やしてみたり、強めてみたらどうだろう。もしかしたら、子どもと呼ばれている若者に目を向けすぎなのかもしれない。逆に、手をかけてはいるが目をかけていないのかもしれない。わからない。
子育ての困難さは、他人からの援助のなさ、孤立と、
子育ては、実は、親自身が自分を作り上げていくプロセスだということに気がついていないことにあるのかもしれない。
それは子どもと親という関係ではなく、一人の人間としての成長に、子どもと呼ばれている命が関わっているということなのであるが。
年寄りは、そのように思った。
子どもと関わり、何を学ぶか。
これは親だけではなく、教師も同じ。
子どもと関わるということは、関わる人が学び続けるということ。
年寄りは、そのように思った。
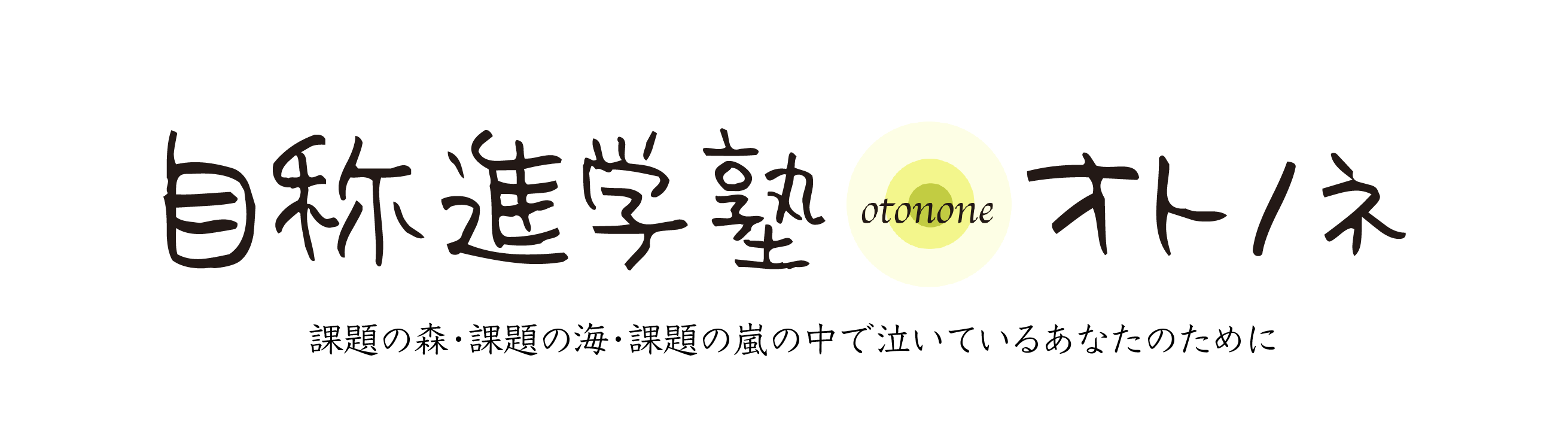
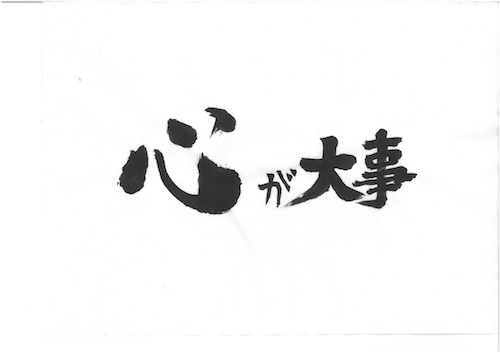

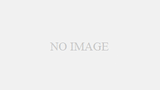
コメント